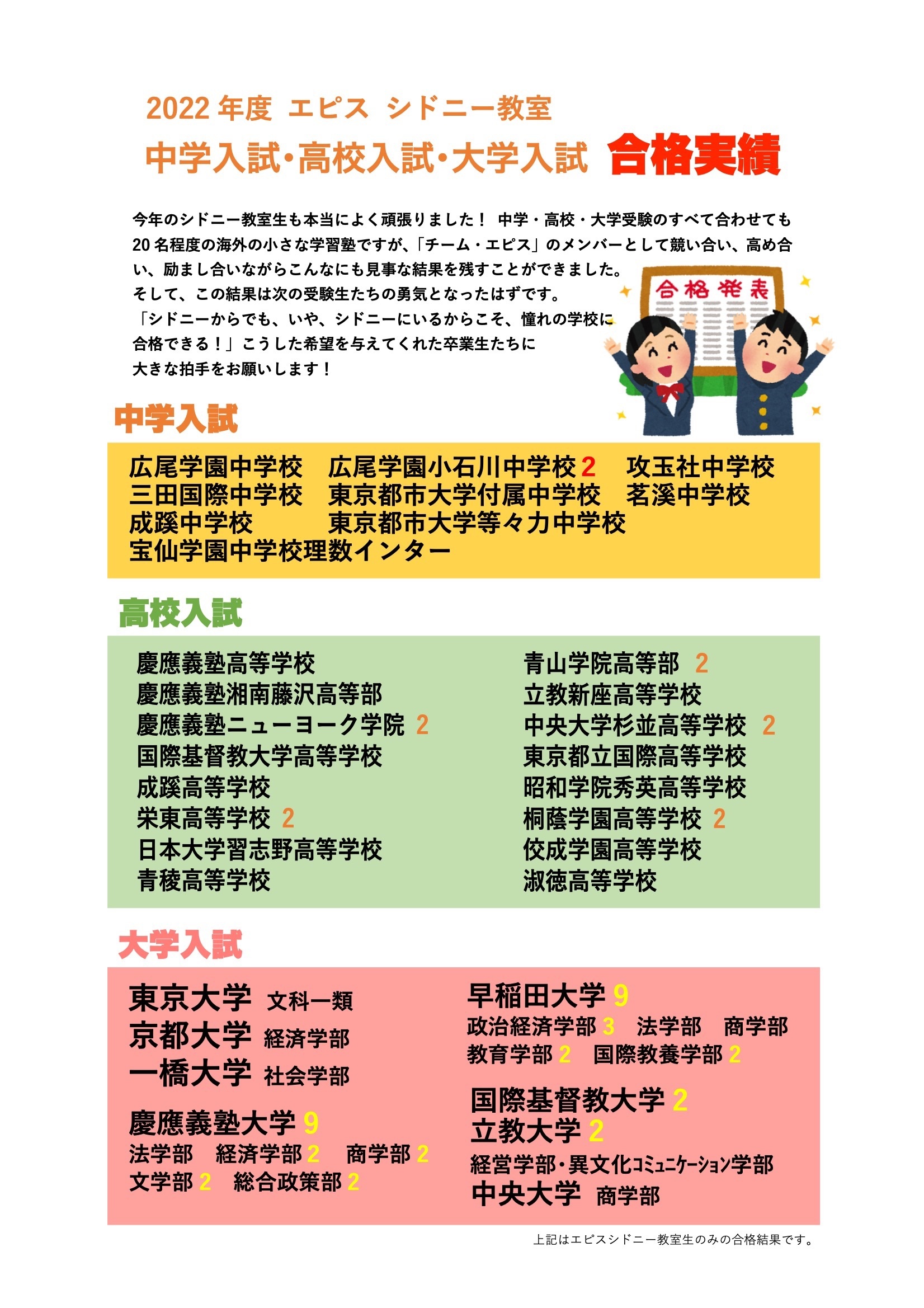多読と知識
みなさん、こんにちは。お久しぶりです、坂本です。
突然ですが、みなさん読書ってされてますか?
私は根っからの読書好きでした。手当たり次第に祖父母が読むような本を読んで過ごしていた頃もあります。
ふと自分の文章を読み返すと、おこがましい話ですが、「あ、〜の文体に似てるな」とか「この語尾は〜の論調みたいだな」とかを感じるわけです笑。ついでに知識もその世界観も盗んできてしまうのです。
私の読書好きは現代の本にとどまりませんでした。古文から洋書(英語に限らず)まで、たくさんの本を読んだ気がします。授業をしていてあちこちに話が飛び火してしまうので、厄介者ですが。。。
ところが、大人になって読書の回数やそれに割く時間は大幅に減ったようです。でも、読書の重要性というものは毎日ヒシヒシと感じています。
*行間力やテーマ力、どういう話の展開や論旨の運び方が「旨い」のか。
小論文やEssay Writingを指導する立場としても欠かせない学びです。昔は先生になれば勉強しなくていいのに、と思ったことがありますが、そんなことはありませんでした。24時間365日、世界からも子どもたちからも学びを得ることができるのです。これはこれで幸せな環境だと、当時の自分に言ってやりたいです。
さて、そんな膨大な知識を仕入れるための読書ですが、本をたくさん読む子の作文や小論文に少し特徴がある気がしてきたのです。
それはズバリ…ストーリー性、です。
自分の体験→一般化というPEELパラグラフの特徴をきっちりと押さえて書けるのです(最初はできなくてもコツは掴みやすい)。これはすごく大事なことだな、と感じています。
そんな多読や知識のための授業を、昼夜熱意をもって展開中です!
みなさんも是非、エピス文庫も授業もご活用ください!
*小学生の国語の授業では、音読や記述を中心に
「読解する授業」を
*小学生の英語の授業では、音読とテーマ力増強を中心に
「英語『で』学ぶ授業」を
*中学生の国語の授業では、学年+αの内容に触れながら
「大人になっても使える日本語と知識のための授業」を
*中学生の英語の授業では、文法ロジックやWritingシステムを軸とした
「実践で(もちろん入試でも)使えるホンモノの英語力のための授業」を
*高等部の小論文の授業では、小論文の書き方はもちろん、
「自分の興味関心を広げる『社会』の学びと日本語のための授業」を
*高等部の英語(TOEFL)の授業では、
「現地校生だからって侮れない非ネイティブのための英語とテーマ力の授業」を
実施しています!
ちなみに私が定期的に読み返したくなる本はこちら
→「The Best Christmas Present in the World」と「きんぴか」などの浅田作品
オススメです!