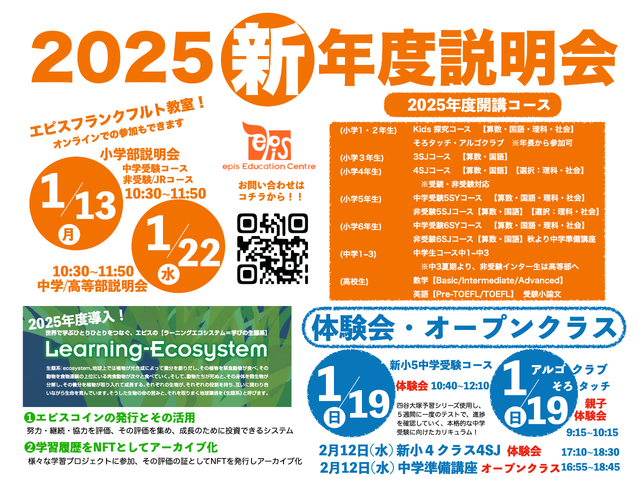日曜日に四谷大塚の全国統一小学生テストがありました。
同時に、「中学受験算数のススメ。」と題して算数セミナーを開催、子どもたちがテストを受験している間に保護者対象に実施しました。
普段なら、仲田と反保が話をするのですが、今回は強力な助っ人、エピス代表の澤村が駆けつけてくれ、熱い話で会場は大いに盛り上がりました。
算数、特に中学受験算数は、いたずらに難しいものではなく、まさに小学生のうちから問題解決力を養うことができる最強と言っても過言ではない題材だと思います。
問題解決力、すなわち生きる力。
そんな素晴らしい力を身につけることができる機会を逃す理由はないと思っています。
しかし、その価値は、なかなか正確に伝わっていないことが多いのが正直なところではないでしょうか。そして、われわれのような教育に携わる人間の中でも、違った認識で捉えられていることも少なくありません。
だからこそ、われわれがその価値を正しく理解し、いや、まずは正しく理解しようとするスタンスを持って取り組み、理解し、伝えていくことが大事なんだということを、改めて感じ入ることができました。
その意味で、このタイミングで算数セミナーを開催できたことは非常に意義深いと思っています。
また、長年の経験を持つ澤村からのメッセージということも説得力を増す要因だったと思います。
算数が苦手とか得意とか関係なく、ぜひあらゆる小学生たちがこの算数を学んでほしい。
そして、そのおもしろさに気がついてほしい。
今まで苦手だと思っていた子どもも、それは周りからの刷り込みだった、自分は苦手ではないということに気が付くはずです。
ヨーロッパでは、フランクフルトからその価値を繋いでいけると良いなと思っています。